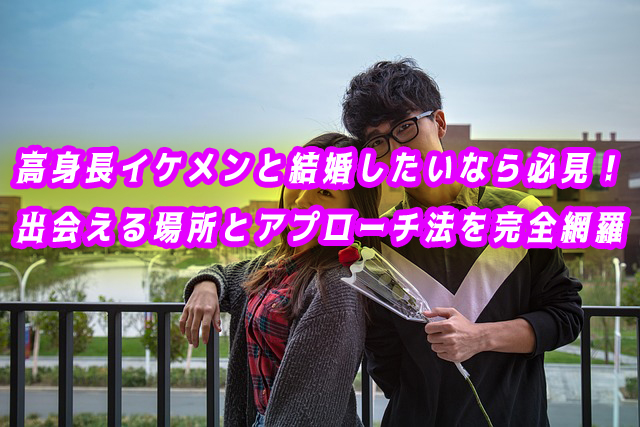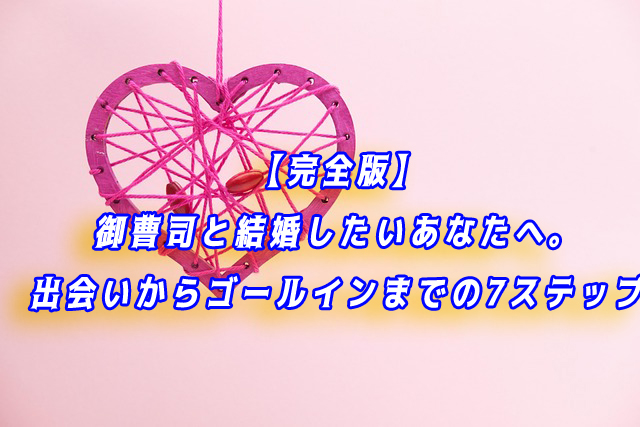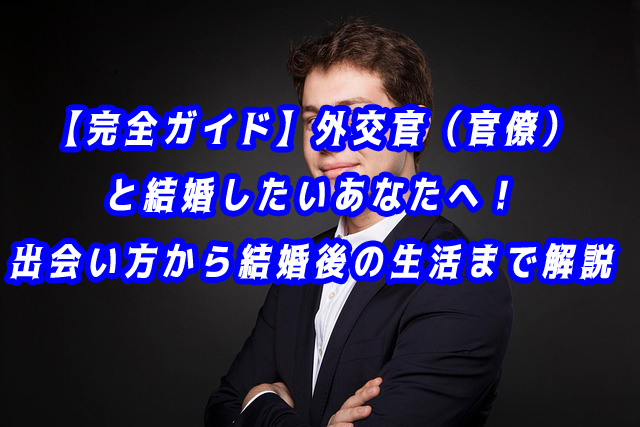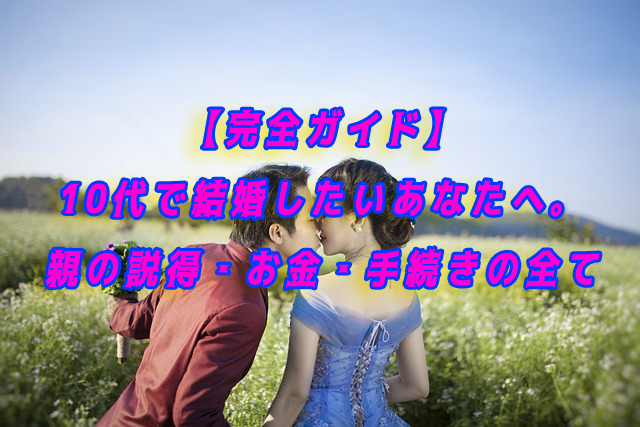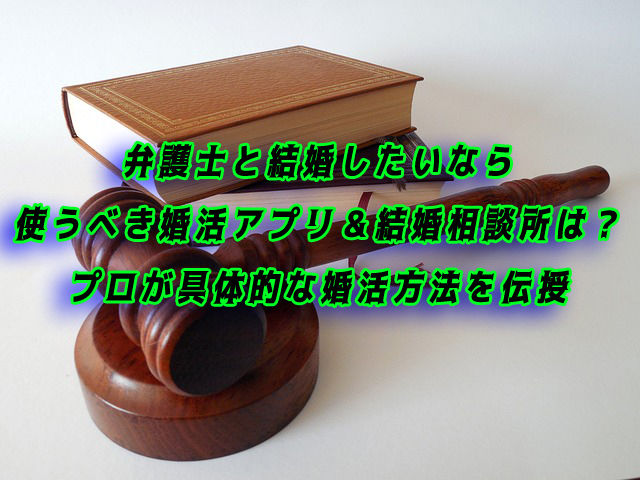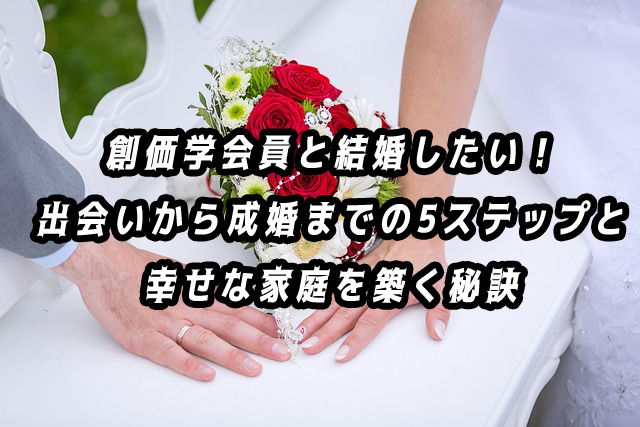
創価学会員の方との結婚を真剣にお考えですか?本記事では、出会いから成婚までの具体的な5ステップを徹底解説します。
非学会員が抱えがちな入信問題や両親の理解、結婚後の生活といった不安や疑問も解消できます。
結論として、お互いの価値観を深く理解し、誠実に対話を重ねることで、幸せな結婚は実現可能です。
この記事を読めば、そのための具体的な方法が全てわかります。
目次
創価学会員との結婚でまず知っておきたい基礎知識
創価学会員の方との結婚を真剣に考え始めたとき、多くの方がさまざまな疑問や少しの不安を感じるのではないでしょうか。
結婚は、お互いの人生観や価値観を深く共有する大切なステップです。
特にパートナーの宗教については、後悔のない選択をするために、事前に正しい知識を得ておくことが非常に重要になります。
この章では、創価学会員との結婚を考える上で、まず押さえておきたい基本的な知識を分かりやすく解説します。
創価学会とはどんな団体か
創価学会は、日本で生まれた仏教系の宗教法人です。
その教えの根幹にあるのは、13世紀の僧侶である日蓮大聖人の仏法です。
会員は、法華経の教えを信じ、日々の生活の中で実践することを目指しています。
創価学会の活動は、個人の幸福追求だけでなく、生命の尊厳を基調とした「平和・文化・教育」の推進に貢献することを大きな目的として掲げており、世界192カ国・地域にメンバーがいます。
政治との関わりにおいては、公明党の支持母体として知られています。
これは、仏法の理念を現実の政治に反映させることを目指すものであり、会員にとって選挙活動は重要な活動の一つと位置づけられています。
団体のより詳しい情報については、公式サイトで確認することをおすすめします。
創価学会員の結婚観と家庭に対する考え方
創価学会員にとって結婚は、単なる二人の結びつき以上の意味を持つことがあります。
多くの学会員は、結婚を「共に信仰を深め、人生の困難を乗り越えていくためのパートナーシップ」と捉えています。
仏法の教えでは「宿命転換」という考え方があり、夫婦で支え合いながら信心に励むことで、互いの宿命をより良い方向へ転換し、幸福な家庭を築いていけると信じられています。
また、家庭は「地域や社会の平和と幸福に貢献するための拠点」と考える傾向もあります。
そのため、夫婦が同じ方向を向いて、社会に貢献していくことを理想とする価値観が根付いています。
もちろん、信仰の度合いや活動への熱心さは人それぞれです。
あなたのパートナーが結婚や家庭に対してどのような考えを持っているのか、先入観を持たずに直接話し合って理解することが何よりも大切です。
非学会員でも創価学会員と結婚はできるのか
結論から言うと、非学会員(学会員ではない方)が創価学会員と結婚することは全く問題なく可能です。
創価学会の教義として、非学会員との結婚を禁じるものはありません。
実際に、パートナーが非学会員という学会員は数多く存在し、幸せな家庭を築いています。
ただし、結婚は当人同士だけの問題ではないことも事実です。
特に相手のご両親が熱心な学会員である場合、あなたの入信を望まれる可能性はゼロではありません。
しかし、それは強制されるものではなく、最終的にはあなた自身の意思が最も尊重されるべきです。
大切なのは、結婚前から入信についての考えをお互いに正直に伝え、理解し合うことです。
非学会員のままで結婚するという選択肢も含め、二人で将来についてしっかりと話し合うことが、幸せな結婚への第一歩となります。
【ステップ1】創価学会員と結婚したい人が出会うための具体的な方法
創価学会員の方との結婚を真剣に考えたとき、まず課題となるのが「出会い」です。
共通の価値観を持つパートナーと巡り会うためには、どのような場所や方法があるのでしょうか。
ここでは、学会員同士の出会いの場から、非学会員の方が学会員と出会うための具体的なアプローチまで、現実的な方法を詳しく解説します。
学会員同士の出会いの場
創価学会員同士の出会いは、主に日々の活動やコミュニティの中にあります。
共通の目的や価値観を持っているため、自然な形で関係が発展しやすいのが特徴です。
ただし、これらの場は本来、出会いだけを目的としたものではなく、信仰活動の一環であることを理解しておくことが大切です。
主な出会いの場としては、以下のようなものが挙げられます。
- 会合や活動を通じて:座談会や各種会合、文化祭や平和活動といった地域でのイベントなど、学会活動に参加する中で顔を合わせる機会は多くあります。共に活動する中で人柄を知り、自然と親しくなるケースは少なくありません。
- 青年部の活動:同世代の男女が集まる青年部の活動は、出会いの機会が豊富な場です。グループでのディスカッションやイベントの企画・運営などを通じて、連帯感が生まれ、恋愛や結婚に発展することがあります。
- 友人・同志からの紹介:学会員のコミュニティはつながりが強いため、信頼できる友人や先輩・後輩の同志から紹介を受けることも一般的です。お互いのことをよく知る人からの紹介なので、安心して会うことができるというメリットがあります。
非学会員が創価学会員と出会うには
非学会員の方が創価学会員と出会う場合、特別な場所に行く必要はありません。
学会員の方も、普段はごく普通に社会生活を送っています。
職場や学校、趣味のサークルなど、一般的な出会いの場にも多くの学会員がいます。
大切なのは、出会いのチャンスを広げ、相手の背景を理解しようとする姿勢です。
ここでは、より結婚を意識した出会いのための具体的な方法をご紹介します。
マッチングアプリや婚活サイトの活用
現代の婚活において、マッチングアプリや婚活サイトは非常に有効なツールです。
利用者数が多いため、出会いの母数を大きく増やすことができます。
創価学会員の方を探す際は、プロフィールの「宗教」に関する項目を上手に活用するのがポイントです。
Pairs(ペアーズ)やwith(ウィズ)といった主要なマッチングアプリでは、任意で宗教を記載できる欄が設けられていることがあります。
また、同じ価値観や趣味を持つ人が集まる「コミュニティ機能」や「グループ機能」で、「創価学会」や関連するキーワードで検索してみるのも一つの方法です。
プロフィールに正直に記載している方や、コミュニティに参加している方は、自身の信仰に理解を求めている可能性が高く、真剣な出会いにつながりやすいでしょう。
検索する際は、相手のプロフィールをよく読み、誠実な人柄かどうかを見極めることが重要です。
メッセージのやり取りが始まったら、早い段階でご自身の結婚観や宗教に対する考え方を正直に伝え、相手の価値観を尊重する姿勢を示すことが信頼関係を築く鍵となります。
結婚相談所の利用
より真剣に、かつ効率的に結婚相手を探したい方には、結婚相談所の利用がおすすめです。
結婚相談所では、入会時に収入や学歴だけでなく、宗教観についても申告する場合がほとんどです。
これにより、お互いの前提が合った状態で出会えるため、交際後のミスマッチを大幅に減らすことができます。
カウンセラーやアドバイザーに「創価学会員の方との結婚を希望します」あるいは「パートナーの宗教活動に理解があります」と明確に伝えることで、条件に合う相手を紹介してもらいやすくなります。
データマッチング型だけでなく、仲人紹介型の相談所であれば、よりきめ細やかなサポートを受けながらお相手探しを進めることが可能です。
大手結婚相談所連盟のIBJ(日本結婚相談所連盟)などに加盟している相談所では、幅広い会員の中から条件に合う人を探せる可能性があります。
まずは無料相談などを利用して、ご自身の希望に沿ったサポートが受けられるかを確認してみると良いでしょう。
友人や知人からの紹介
最も信頼性が高く、安心感のある出会い方が、友人や知人からの紹介です。
もしあなたの周りに創価学会員の友人がいるなら、結婚を真剣に考えていることを正直に相談してみるのが一番の近道かもしれません。
紹介のメリットは、紹介者がお互いの人柄や性格をある程度把握しているため、相性の良い相手と出会える可能性が高い点です。
また、第三者を介すことで、聞きにくいことも代わりに確認してもらえたり、関係がうまくいくようにサポートしてもらえたりすることもあります。
もちろん、これは非常にプライベートな話なので、誰にでも気軽に頼めることではありません。
日頃から信頼関係を築いている、口が堅い友人や知人を選ぶことが大切です。
「創価学会の方とのご縁を探しているんだけど、もし周りに素敵な人がいたら紹介してほしい」と、誠実な姿勢でお願いしてみましょう。
【ステップ2】交際中に確認すべき大切なこと
創価学会員の方との交際が順調に進み、結婚を意識し始めたら、お互いの将来のために必ず確認しておきたい大切なことがあります。
宗教は個人の価値観の根幹に関わるデリケートなテーマだからこそ、見て見ぬふりをするのではなく、誠実に向き合うことが不可欠です。
ここでは、交際中に確認・共有すべき3つの重要なポイントを具体的に解説します。
相手の信仰心や活動レベルを理解する
まず最も重要なのが、お相手の信仰心や学会活動への関わり方を具体的に理解することです。
「創価学会員」と一括りに言っても、その信仰のあり方は人それぞれ大きく異なります。
ご両親が入信しているだけで本人は活動に熱心ではない方もいれば、組織で役職に就き、熱心に活動されている方もいます。
この違いが、結婚後の生活スタイルに直接影響を与えるため、交際期間中にしっかりと確認しておく必要があります。
相手を問い詰めるような聞き方ではなく、「あなたのことをもっと深く知りたいから教えてほしい」という姿勢で、以下のような点を自然な会話の中で尋ねてみましょう。
- 勤行(ごんぎょう)の習慣:毎日、朝晩の勤行を行っているか。もし行っている場合、時間はどれくらいか。
- 会合への参加頻度:座談会や勉強会など、各種会合にどれくらいの頻度で参加しているか。(例:週に1回、月に数回など)
- 組織での役職:青年部や婦人部などで、何か役職に就いているか。役職があると、活動に費やす時間や責任も大きくなる傾向があります。
- 聖教新聞の購読:聖教新聞を購読しているか。また、結婚後も購読を続ける意向があるか。
- 選挙活動への関わり方:選挙の時期に、友人・知人への投票依頼(いわゆるF活・フレンド票活動)などをどの程度行うのか。
- 財務(寄付)について:年に一度行われる財務(寄付)に、どの程度協力しているか。
これらの質問を通じて得た答えを基に、その活動レベルが自分のライフスタイルや価値観と共存できる範囲内かどうかを冷静に考えてみましょう。
もし、相手の活動が自分の想像以上に熱心だったとしても、すぐに「無理だ」と判断するのではなく、まずは事実として受け止め、次のステップである「宗教観の話し合い」につなげていくことが大切です。
相手の価値観の根幹をなす部分を理解しようと努める姿勢が、信頼関係を深める第一歩となります。
お互いの宗教観について話し合う
相手の信仰について理解を深めたら、次はお互いの宗教観についてオープンに話し合うステップです。
これは、相手の信仰を評価するためではなく、お互いの価値観の違いを認識し、尊重し合うための重要なプロセスです。
あなたがもし特定の宗教を信仰していない「無宗教」であるなら、そのことを正直に伝えましょう。
話し合いを始める前に、まずは自分自身の考えを整理しておくことが大切です。
- 自分は「無宗教」だが、お盆に墓参りをしたり、クリスマスを祝ったり、初詣に行ったりすることに抵抗はないか。
- 宗教や信仰というものを、自分はどのように捉えているか。
- 相手の信仰活動に対して、どこまでなら理解・協力できると感じるか。
自分の考えがまとまったら、リラックスした雰囲気の中で、「結婚を真剣に考えているからこそ、大切な価値観について話しておきたい」と切り出してみましょう。
その際、以下の点を意識すると、建設的な話し合いにつながります。
- 相手の信仰を否定しない:たとえ自分には理解できない部分があったとしても、「それはおかしい」といった否定的な言葉は避けましょう。
- 自分の考えを押し付けない:「あなたにも無宗教になってほしい」といった要求は、相手のアイデンティティを否定することになりかねません。
- 「I(アイ)メッセージ」で伝える:「(あなたは)なぜそんなに活動するの?」という聞き方ではなく、「(私は)あなたの活動について、こう感じている」というように、自分の気持ちを主語にして伝えると、相手も受け入れやすくなります。
この話し合いを通じて、お互いが「違う」ということを前提に、どうすれば心地よい関係を築けるかを探っていくことが目的です。
お互いの価値観を尊重し合えるという確信が持てれば、それは結婚に向けた大きな前進となるでしょう。
結婚に対する自分の気持ちを正直に伝える
相手の信仰を理解し、お互いの宗教観を共有した上で、最終的に「結婚」に対する自分の正直な気持ちを伝える必要があります。
特に、非学会員の方が最も気になるであろう「入信」の問題については、決して曖昧にせず、自分の意思を明確に伝えることが極めて重要です。
もし、あなたに「入信するつもりはない」という固い意志があるなら、そのことを誠実に、しかしはっきりと伝えなければなりません。
「好きだから」「相手を悲しませたくないから」といった理由で気持ちに嘘をついてしまうと、後々必ず大きな問題となってしまいます。
伝える際には、ただ「入信はしない」と突き放すのではなく、譲歩できる点と譲れない点を具体的に示すと、相手もあなたの気持ちを理解しやすくなります。
<伝え方の例>
「あなたの信仰は、あなたにとって大切なものだと理解しています。その気持ちは心から尊重したいと思っています。ただ、私自身があなたの信仰を受け入れて入信する、ということはできません。これは、私の人生観に関わる正直な気持ちです。
でも、あなたが勤行をすることや会合に参加することは止めないし、むしろ応援したいと思っています。聖教新聞を読むのも自由です。ただ、私や将来生まれてくる子供に入信を強制することだけはしないでほしい。子供の信仰については、本人が大きくなってから自分の意思で決めさせてあげたいと考えています。この点について、あなたの考えを聞かせてもらえますか?」
このように、相手への尊重を示しつつ、自分の譲れない一線を明確に伝えることで、お互いが納得できる着地点を見つけられる可能性が高まります。
この話し合いは、二人が本当に生涯を共に歩んでいけるパートナーであるかを見極めるための、最後の、そして最も重要な確認作業と言えるでしょう。
【ステップ3】結婚の壁を乗り越える 入信問題と両親への挨拶
創価学会員の方との交際が順調に進み、いよいよ結婚を具体的に考え始めると、多くの方が「宗教」というテーマに改めて向き合うことになります。
特に「入信」の問題と、お互いの「両親への挨拶」は、結婚までの道のりにおける大きな関門と感じるかもしれません。
しかし、これらは二人で誠実に向き合い、対話を重ねることで乗り越えられる課題です。
ここでは、不安を解消し、円満に結婚へと進むための具体的なステップを解説します。
入信は必須?正直な気持ちを伝える重要性
創価学会員の方と結婚するにあたり、最も気になる点の一つが「自分も入信しなければならないのか?」ということでしょう。結論から言うと、結婚相手が入信する(創価学会員になる)ことは、必ずしも必須ではありません。
創価学会の教えの根幹には、個人の意思を尊重するという考え方があります。
そのため、パートナーの意思に反して入信を強要することは、本来の教えとは異なります。実際に、パートナーが非学会員のまま幸せな結婚生活を送っているご夫婦はたくさんいます。
ここで最も大切なのは、お互いの正直な気持ちを伝え合うことです。
まずはパートナーに、結婚相手の入信についてどう考えているのかを尋ねてみましょう。
「入信してくれたら嬉しいけれど、強制はしない」「信仰を理解してくれればそれで良い」など、相手の考えは様々です。
その上で、あなた自身の気持ちを正直に、そして誠実に伝えてください。
「あなたの信仰は尊重したいけれど、私自身が現時点で入信する考えはない」という気持ちであれば、それを正直に話すことが信頼関係の基礎となります。
曖昧な返事をしたり、その場しのぎで話を合わせたりすることは、将来的に大きな問題に発展しかねません。
入信しないという選択をする場合、その理由や、代わりにどう協力していきたいか(例:パートナーの活動への理解を示す、など)を具体的に伝えることで、相手も安心してくれるでしょう。
自分の両親に理解してもらうための伝え方
自分の両親に、結婚相手が創価学会員であることを伝えるのは、勇気がいることかもしれません。
宗教に対して特定のイメージを持っていたり、馴染みがなかったりする場合、ご両親が心配される可能性も考えられます。
大切なのは、伝え方の順序と準備です。
いきなり「創価学会員の人と結婚する」と切り出すのではなく、まずは結婚したい大切な人がいることを伝え、その相手がどれほど素晴らしい人物であるかを具体的に話しましょう。
仕事への姿勢、あなたへの愛情、誠実な人柄など、ご両親が「そんな素敵な人なら会ってみたい」と思えるような情報を先に伝えることがポイントです。
その上で、相手の信仰について説明します。
この時、あなた自身が創価学会に対して正しい知識を持っていることが重要です。
インターネット上の不確かな情報や偏見で語るのではなく、パートナーから直接聞いた話や、二人で話し合った内容を元に説明しましょう。
ご両親から予想される質問(「入信させられるの?」「お金はかかるの?」「選挙活動は?」など)に対しては、二人で事前に話し合った内容を元に、明確に答えられるように準備しておくと、ご両親の不安を和らげることができます。
「入信するつもりはないこと」「家庭の経済状況を圧迫するような寄付はしないこと」など、二人で決めたルールを具体的に伝えるのが効果的です。
すぐに理解を得られなくても焦らず、時間をかけて対話を続ける姿勢を見せることが、最終的な信頼に繋がります。
相手の両親へ挨拶する際の心構えと注意点
パートナーのご両親への挨拶は、どんな結婚でも緊張する一大イベントです。
相手が熱心な創価学会員である場合、さらに身構えてしまうかもしれませんが、基本的なマナーと誠実な姿勢が重要であることに変わりはありません。
心構えとして大切なこと:
-
- 敬意を払う姿勢:パートナーが大切にしているご両親であり、そのご両親が大切にしている信仰です。その両方に対して、心からの敬意を払う姿勢で臨みましょう。
- 誠実であること:自分を偽らず、誠実な態度で接することが信頼を得る一番の近道です。清潔感のある服装や礼儀正しい言葉遣いは、その誠実さを示す第一歩です。
- パートナーを立てる:ご両親にとっては、あなた以上に自分の子どもの幸せが一番の関心事です。パートナーを心から大切に思っている気持ちが伝われば、ご両親も安心してくれるでしょう。
挨拶当日の注意点:
宗教に関する話題は非常にデリケートです。
相手のご両親から聞かれない限り、自分から積極的にその話題に触れるのは避けた方が無難でしょう。
もし信仰について質問された場合は、嘘をつかずに正直に、かつ丁寧に答えることが重要です。
例えば、「〇〇さん(パートナー)の信仰については、お話を伺って理解を深めていきたいと思っています。
私自身は入信する考えはございませんが、〇〇さんの活動は尊重し、家族として支えていきたいです」といったように、敬意と自分の意思を明確に伝えましょう。
絶対に避けるべきなのは、創価学会の活動や教義に対して否定的な意見を述べることです。
たとえ疑問に思うことがあっても、その場で反論するのは得策ではありません。
事前にパートナーと「もしこんなことを聞かれたら、こう答えよう」と綿密に打ち合わせをしておき、当日はパートナーにうまくフォローしてもらえるように協力体制を築いておくことも大切です。
【ステップ4】成婚へ向けて二人で準備すること
お互いの気持ちが固まり、両親への挨拶も済んだら、いよいよ成婚へ向けた具体的な準備が始まります。
このステップは、二人の新しい生活をスムーズにスタートさせるための大切な期間です。
特に創価学会員との結婚では、宗教観が関わる部分について事前にしっかりと話し合い、共通認識を持っておくことが幸せな結婚生活の鍵となります。
後々の「こんなはずじゃなかった」を防ぐためにも、一つひとつ丁寧に準備を進めていきましょう。
結婚式のスタイルを話し合う
結婚式は、二人が夫婦になることを誓い、大切な人たちに報告する重要な儀式です。
創価学会員との結婚では、いくつかの選択肢が考えられます。
どちらか一方の意見を押し通すのではなく、二人と両家が心から納得できるスタイルを選びましょう。
学会員同士の結婚式
創価学会員同士のカップルの場合、創価学会の会館などで執り行われる「仏前結婚式(仏式)」を選ぶのが一般的です。
同志である多くの友人たちから祝福を受けられる、温かい雰囲気の式となります。
厳かな読経・唱題や指輪の交換、誓いの言葉などを通じて、仏法を根本に新たな人生を歩み出す決意を固めます。
非学会員との結婚式
パートナーが非学会員の場合、結婚式の選択肢はさらに広がります。
大切なのは、お互いの価値観と両家の意向を尊重することです。
- 人前式(じんぜんしき): 特定の宗教によらないため、最も選ばれやすいスタイルです。列席してくれたゲスト全員に結婚を誓い、証人になってもらいます。宗教色がないため、両家の親族も安心して参加しやすいのが大きなメリットです。
- 神前式やキリスト教式: 非学会員のパートナーやそのご家族が希望する場合、神前式やキリスト教式を選ぶことも可能です。その際は、学会員のパートナーが相手の家の宗教儀式に参加することへの理解を示し、お互いの家族ともよく話し合うことが重要です。
- フォトウェディングや食事会: 儀式にこだわらず、ウェディングドレスや和装で記念写真を撮るフォトウェディングや、親しい身内だけで食事会を開くという形も人気です。
どのスタイルを選ぶにしても、「なぜそのスタイルが良いのか」を二人で話し合い、両家の両親にも事前に相談して理解を得ておくと、当日を晴れやかな気持ちで迎えられます。
結婚後の生活ルールを決めておく
価値観のすり合わせは、結婚生活を円満に続けるために不可欠です。
特に宗教活動に関しては、結婚前に具体的なルールを決めておくことで、無用な衝突を避けられます。
お互いがストレスなく、心地よく暮らしていくための大切な話し合いです。
勤行や会合への参加について
創価学会員にとって、朝晩の「勤行(ごんぎょう)」と「唱題(しょうだい)」は、日々の生活の基本となる大切な仏道修行です。
また、地域の同志と集う「座談会」などの会合も、信仰を深める上で重要な活動です。
非学会員のパートナーは、これらの活動にどう関わるかを事前に決めておきましょう。
- 勤行の時間: 学会員のパートナーが勤行をしている間、非学会員のパートナーはどう過ごすか(例:「静かに見守る」「別の部屋でテレビを見る」「気にせず家事をする」など)を決めておくと、お互いに気まずい思いをしなくて済みます。
- 会合への参加: 会合への参加は強制されるものではありません。「一切参加しない」「興味があるテーマの時だけ参加してみる」「地域のイベントなど、宗教色の薄いものなら参加する」など、自分の気持ちを正直に伝え、どこまで関わるかの線引きを明確にしておきましょう。
聖教新聞の購読や選挙活動について
日常生活に密接に関わるテーマとして、「聖教新聞」と「選挙活動」についても話し合っておく必要があります。
- 聖教新聞の購読: 聖教新聞は、創価学会の日刊機関紙です。学会員のパートナーが購読を希望する場合、非学会員のパートナーがそれを読む義務はありません。「購読はするが、読む・読まないは個人の自由」「新聞の管理は学会員のパートナーが行う」といったルールを決めておくと良いでしょう。
- 選挙活動: 創価学会は支援政党として公明党を応援しており、選挙期間中には知人・友人に投票を依頼する活動(いわゆるF票活動)を行うことがあります。ここで最も大切なのは、日本国憲法で保障されている「思想・信条の自由」をお互いに尊重することです。「誰に投票するかは個人の自由であり、一切干渉しない」「自分の友人関係にまで支援依頼を広げない」といった約束を明確に交わしておくことが、信頼関係を維持するために極めて重要です。
これらのルール作りは、相手を縛るためではなく、二人がお互いを尊重し、理解を深めるための共同作業です。
愛情と信頼をベースに、正直な気持ちで話し合いましょう。
【ステップ5】創価学会員と幸せな家庭を築くための秘訣
結婚はゴールではなく、二人で幸せな家庭を築いていくための新たなスタートです。
特に、創価学会員と非学会員のカップルの場合、信仰という大切な価値観を背景に持つため、結婚後の継続的な努力と理解がより一層重要になります。
これまでのステップを経て結ばれた二人が、末永く幸せな結婚生活を送るための3つの秘訣をご紹介します。
お互いの価値観を尊重し続ける
幸せな家庭の土台となるのは、何よりもお互いの価値観を尊重し続ける姿勢です。
パートナーの信仰は、その人の生き方や人格を形成する大切な要素の一部です。
それを否定することは、相手そのものを否定することにつながりかねません。
非学会員のパートナーは、相手が勤行や会合に参加することを「自分より学会活動を優先している」と捉えるのではなく、「パートナーが自分らしくあるために必要な時間」と理解するよう努めましょう。
一方で学会員のパートナーも、相手が信仰を持たない自由を尊重し、入信や活動への参加を強要しないことが鉄則です。
お互いが「相手を変えよう」とするのではなく、「相手を深く理解しよう」と歩み寄る気持ちが、信頼関係を育みます。
「自分にとっての当たり前」が、相手にとってはそうではないことを常に意識し、違いを認め合うことが、穏やかな家庭環境を築く第一歩となります。
日頃からコミュニケーションを欠かさない
価値観が異なるからこそ、他の夫婦以上に丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
「言わなくてもわかるはず」という思い込みは、すれ違いや誤解を生む原因になります。
日々のささいな出来事から、信仰に関する少しデリケートな話題まで、何でも話し合える関係性を築きましょう。
例えば、選挙期間や大きな会合がある時期など、学会の活動が活発になるタイミングについては、事前にスケジュールを共有し、家庭内でどのような協力が必要か話し合っておくとスムーズです。
また、活動に参加して感じたことや、逆に非学会員のパートナーが抱いている疑問や不安などを、お互いに正直に伝え合う時間を持つことも大切です。
宗教の話だけでなく、二人共通の趣味を楽しんだり、将来の夢を語り合ったりする時間も意識的に作り、夫婦としての絆を深めていく努力を続けましょう。
感謝の言葉を忘れずに伝え合うことも、良好な関係を維持するシンプルな秘訣です。
周囲の人々と良好な関係を築く
結婚は二人だけの問題ではなく、お互いの家族やコミュニティとの関わりも生まれます。
周囲の人々と良好な関係を築くことは、夫婦二人を支える大きな力になります。
まず、お互いの両親や親戚との関係です。相手の家族が学会員である場合、冠婚葬祭のしきたりや親戚付き合いの中で、学会の文化に触れる機会もあるでしょう。
すべてに同調する必要はありませんが、敬意を払い、誠実な態度で接することが大切です。
自分の両親には、パートナーの良いところや結婚生活の楽しい様子を日頃から伝えることで、宗教に対する漠然とした不安や偏見を和らげる助けになります。
また、パートナーが所属する地域の学会員の方々と顔を合わせることもあるかもしれません。
過度に壁を作るのではなく、挨拶を交わすなど、パートナーの友人・知人として節度ある態度で接することで、パートナーの立場を守り、地域コミュニティの中で孤立させない配慮にもつながります。
もし過度な勧誘など、何か困ったことが起きた場合は、一人で抱え込まずに、まずは一番の味方であるパートナーに相談しましょう。
創価学会員との結婚に関するよくある質問
創価学会員の方との結婚を考え始めると、信仰に関する具体的な疑問や不安が次々と浮かんでくることでしょう。
特に、お子さんのこと、親戚付き合い、金銭的な側面は、結婚生活に直結する重要な問題です。
ここでは、多くの方が抱く代表的な3つの質問について、具体的にお答えしていきます。
事前に正しい知識を得て、パートナーとの対話に役立ててください。
子供が生まれたら入信は必要ですか
結論から言うと、お子さんを入信させるかどうかは、夫婦の話し合いと本人の意思によって決めることであり、強制されるものではありません。創価学会の教えにおいても、本人の意思に基づかない信仰は推奨されていません。
実際には、親が学会員である家庭で育ったお子さん(いわゆる「学会2世・3世」)は、自然な流れで入会することが多いのも事実です。
しかし、それはあくまでご両親の方針によるものです。
非学会員のパートナーとしては、将来生まれてくる子供の信仰について、どう考えているかを事前にパートナーとしっかり話し合っておくことが極めて重要です。
例えば、「物心がついたら、子供自身の意思で決めさせたい」「無理に会合などに連れて行くことはしない」といった具体的なルールを二人で決めておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
お子さんの将来に関わる大切なことだからこそ、お互いの価値観を尊重し、納得できる結論を見つけるための対話を重ねましょう。
親戚付き合いで気をつけることはありますか
創価学会員の方との結婚における親戚付き合いは、基本的なマナーは一般的な結婚と変わりませんが、宗教に対する理解と配慮が求められる場面があります。
特に「相手の親族」と「自分の親族」への対応は、それぞれポイントが異なります。
まず、パートナーの親族も学会員である可能性が高いでしょう。
その場合、法事などの冠婚葬祭が創価学会の形式(友人葬など)で行われたり、日常会話の中に信仰に関する話題が出たりすることがあります。
無理に合わせる必要はありませんが、相手の信仰や価値観を否定するような言動は避け、一人の人間として誠実に向き合う姿勢が大切です。
相手の家族が大切にしているものを、自分も尊重するという気持ちが、良好な関係を築く鍵となります。
一方で、ご自身の親族が創価学会に対して理解がない、あるいは偏見を持っている場合もあるかもしれません。
その際は、まずパートナーの人柄や誠実さを丁寧に伝え、宗教だけで判断しないでほしいという気持ちを真摯に訴えましょう。
結婚前から「宗教の勧誘はしない」「家庭内のルールは二人で決める」といった約束事を明確にしておき、それを両親に伝えることで、安心してもらえるケースもあります。
財務などの寄付は強制されますか
創価学会には「財務」と呼ばれる寄付の制度がありますが、これは完全に任意のものであり、強制されることは一切ありません。
財務は、広宣流布(仏法を広く宣べ伝えること)を支えるためのもので、年に一度、期間を定めて行われます。
寄付をするかしないか、また金額をいくらにするかも、すべて個人の自由な意思と経済状況に委ねられています。
この点については、創価学会の公式サイトでも「会員がそれぞれの発意と歓喜の心で、広宣流布を支えるために行うもの」と明記されており、強制ではないことが示されています。
ただし、パートナーが熱心な学会員である場合、家計の中から財務を行うことを考えている可能性があります。
大切なのは、その事実を隠さずにオープンに話し合うことです。
家計を共にする夫婦として、年間の財務をどの程度見込むのか、生活費とのバランスをどう取るのかなど、金銭計画について事前にしっかりと話し合い、お互いが納得できるルールを決めておくことが、健全な家庭を築く上で不可欠です。
まとめ
創価学会員との結婚は、非学会員であっても可能です。
最も大切なのは、信仰を含むお互いの価値観を深く理解し、尊重し合うこと。
入信問題や結婚後の生活ルールなど、不安な点は事前に正直な対話で解決策を見出す姿勢が、幸せな家庭を築く秘訣です。
本記事で解説した出会いから成婚までの5つのステップを参考に、二人で協力して素敵な未来を築いてください。