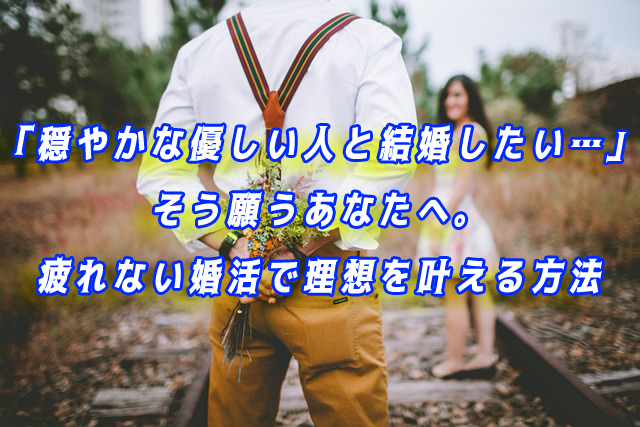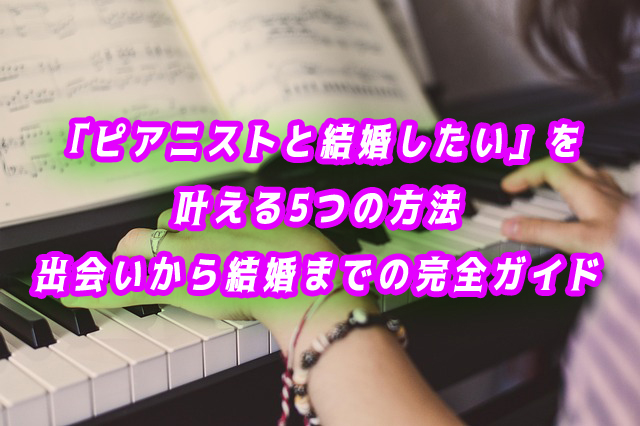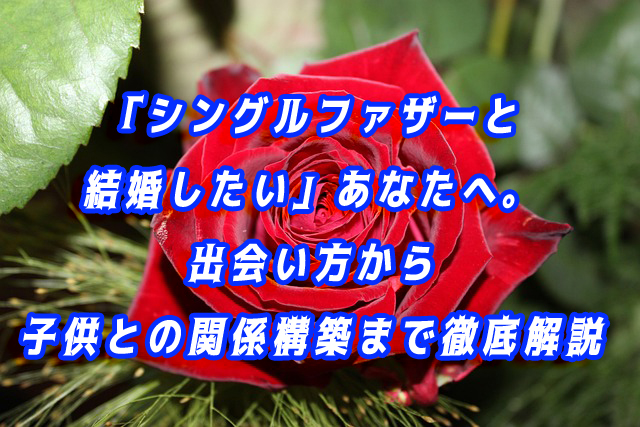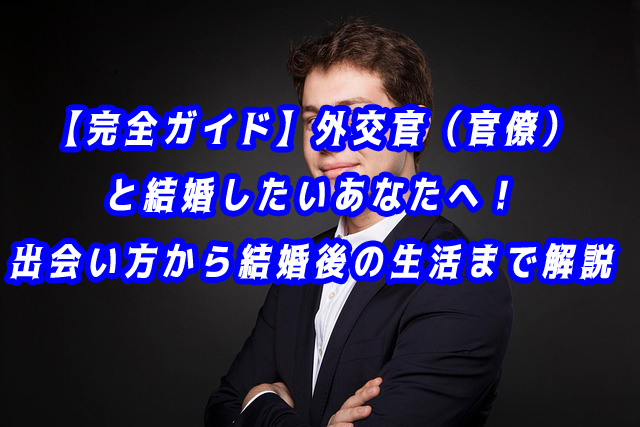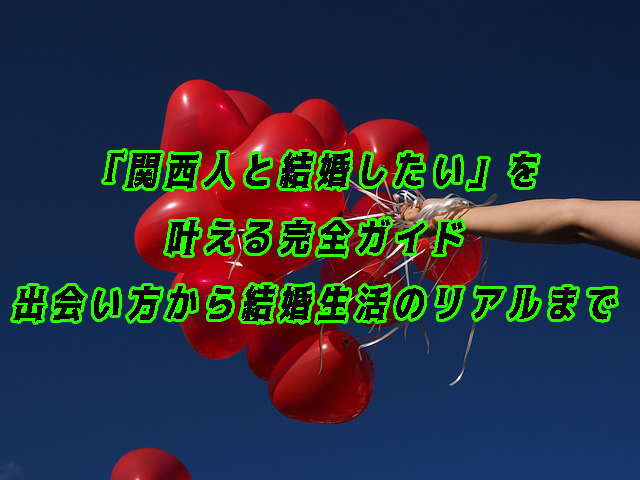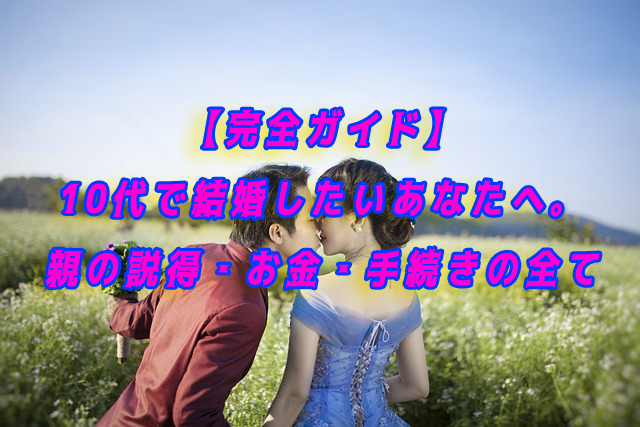
「10代で結婚したい」と真剣に考えるあなたへ。
その決意は決して特別なことではありません。
この記事を読めば、最大の壁である親の説得方法から、必要な費用と貯金術、婚姻届の正しい手続きまで、あなたが知りたい全てが分かります。
10代の結婚は、正しい知識と計画的な準備、そして強い覚悟があれば実現可能です。不安を解消し、幸せな一歩を踏み出すための完全ガイドです。
目次
10代で結婚したいと考えるのはおかしいことじゃない
「大好きな人と、1日でも早く結婚してずっと一緒にいたい」
もしあなたが今そう考えているなら、その気持ちは決して特別なものでも、おかしいものでもありません。
周りの友人や大人からは「まだ早い」「人生経験を積んでからでも遅くない」といった言葉をかけられ、自分の気持ちが間違っているのではないかと不安になっているかもしれません。
しかし、人を愛し、生涯を共にしたいと願う気持ちに、年齢は関係ありません。大切なのは、その純粋な気持ちと向き合い、結婚という現実を冷静に見つめることです。
この章では、まず10代の結婚に関する客観的なデータと、若くして結婚を決意する人たちの主な理由を見ていきましょう。
あなたのその想いを肯定し、未来へ踏み出すための第一歩です。
10代の結婚に関する現状データ
現代の日本では、10代で結婚するカップルは決して多くはありません。
晩婚化が進み、平均初婚年齢は男女ともに上昇傾向にあります。
しかし、ゼロではないのも事実です。
厚生労働省が発表した「令和4年(2022年)人口動態統計」によると、この年に結婚した夫婦のうち、夫または妻が19歳以下だったケースは以下のようになっています。
- 夫が19歳以下の婚姻件数:761組
- 妻が19歳以下の婚姻件数:3,514組
(出典:e-Stat 政府統計の総合窓口 人口動態調査 2022年)
この数字を見ると、年間で数千組の10代が結婚という決断をしていることがわかります。
全体の婚姻件数から見れば少数派かもしれませんが、あなたと同じように若くしてパートナーとの人生を歩み始めることを選んだ人たちが、確かに存在しているのです。
この事実を知るだけでも、少し心が軽くなるのではないでしょうか。
若くして結婚を決意する主な理由
10代で結婚を決意する背景には、カップルそれぞれの様々なストーリーがあります。
周りから見れば「早すぎる決断」に思えても、本人たちにとっては確固たる理由があるのです。
ここでは、若くして結婚を決めるカップルによく見られる理由をいくつかご紹介します。
「この人しかいない」という強い確信
純粋にお互いを深く愛し、「運命の人だ」と確信しているケースです。
年齢に関係なく、この人と生涯を共にしたいという強い気持ちが、結婚への大きな原動力となります。
周りが何を言おうと、ふたりの間には揺るぎない絆と信頼関係が築かれているのです。
妊娠がきっかけとなる(授かり婚)
新しい命を授かったことをきっかけに、結婚を決意するカップルも少なくありません。
これは「できちゃった結婚」と表現されることもありますが、ふたりで親になる責任を果たし、子どもをしっかり育てていこうという覚悟の表れでもあります。
愛する人との間に生まれた命を大切にしたいという想いが、結婚という形に繋がります。
早く自立して二人で生活を始めたい
親元を離れ、経済的にも精神的にも自立した生活を一日でも早く始めたいという想いから結婚を選ぶカップルもいます。
特に、パートナーと協力し合って困難を乗り越え、自分たちの力で家庭を築いていくことに強い憧れや価値を見出している場合に多い理由です。
パートナーが心の支えである
家庭環境や個人的な悩みなど、何らかの困難な状況に置かれているとき、パートナーの存在が唯一の心の支えになっている場合があります。
そのような状況下では、法的な結びつきを持つことで、より強い安心感を得たい、正式な家族としてお互いを支え合っていきたいと考えるのは自然なことです。
これらの理由に、良いも悪いもありません。どんなきっかけであれ、ふたりが真剣に将来を考え、結婚という選択肢に至ったこと自体が尊い決断です。
大切なのは、その決断に責任を持ち、これからの人生をどう歩んでいくかを具体的に考えていくことです。
【冷静に考えよう】10代で結婚するメリットとデメリット
「大好きな人と、1日でも早く家族になりたい」その気持ちは、とても純粋で素敵なものです。
しかし、結婚は人生を大きく左右する決断。
特に10代での結婚は、良い面もあれば、乗り越えなければならない壁もたくさんあります。
感情だけで突っ走って後悔しないために、まずはメリットとデメリットの両方を冷静に見つめ、自分たちの未来を具体的に想像してみましょう。
10代で結婚する4つのメリット
若くして結婚することには、他の世代では得難い特別なメリットがあります。
まずは、希望に満ちた良い側面に目を向けてみましょう。
若いうちからパートナーと人生を歩める
最大のメリットは、人生で最も多感でエネルギーに溢れる時期を、愛するパートナーと共に過ごせることです。
楽しいことも、辛いことも、二人で分かち合いながら乗り越えていく経験は、何物にも代えがたい深い絆を育みます。
20代、30代と年を重ねるごとに、共に成長してきた歴史が二人の関係をより強固なものにしてくれるでしょう。
長い人生を、最初から最高の味方と一緒に歩み始められるのは、大きな幸福と言えます。
体力があるうちの子育て
将来的に子どもを望むカップルにとって、若さと体力は大きなアドバンテージになります。
一般的に、10代〜20代前半は妊娠・出産における身体的な負担が少なく、産後の回復も早い傾向にあります。
また、子育ては想像以上に体力勝負。夜泣きへの対応や、公園で子どもを追いかけ回すなど、元気いっぱいの我が子と向き合うには体力が必要です。
子どもが成人する頃、親である自分たちもまだ若いため、その後のセカンドライフを長く楽しめるという見方もできます。
経済的な自立心が早くから芽生える
結婚すれば、親に頼らず自分たちの力で生計を立てていく必要が出てきます。
この「自分たちで家庭を築く」という責任感が、経済的な自立心を早くから育ててくれます。
同年代の友人がまだお小遣いや仕送りで生活している中で、家計の管理や節約、将来のための貯蓄などを真剣に考えるようになります。
二人で協力してお金を管理し、目標を達成していく過程は、確かな自信と生活力を身につける貴重な機会となるでしょう。
お互いを高め合って成長できる
10代は、価値観や人間性が大きく形成される大切な時期です。
そんな変化の時期を共に過ごすことで、お互いの未熟な部分を補い合い、支え合いながら一人の人間として大きく成長できます。
パートナーの夢を応援したり、時には意見をぶつけ合ったりしながら、社会的な責任感や困難に立ち向かう強さを育んでいけるのです。
二人で一つのチームとして未来を切り拓いていく経験は、精神的な成熟を促し、人間的な深みを与えてくれるはずです。
知っておくべき5つのデメリットと後悔しやすい点
メリットの裏には、必ずデメリットが存在します。
特に10代の結婚では、現実的な問題が多く、これらを直視せず進むと「こんなはずじゃなかった」という後悔につながりかねません。
厳しい現実もしっかりと受け止めましょう。
経済的な基盤が不安定になりやすい
最も大きな壁は、経済的な問題です。
高校生や大学生、あるいは社会人になったばかりの10代では、収入が低く不安定なケースがほとんどです。
アルバイト収入だけでは、家賃、光熱費、食費といった生活費を安定して払い続けるのは非常に困難でしょう。
十分な貯蓄がないまま新生活を始めると、病気や怪我、冠婚葬祭といった急な出費に対応できず、すぐに行き詰まってしまう可能性があります。
お金の苦労が、二人の関係に亀裂を入れる最も大きな原因になり得ます。
親や周囲からの反対や偏見
「人生経験が浅すぎる」「経済的に自立できていない」といった理由から、両親や親戚から猛反対される可能性は非常に高いでしょう。
あなたたちの将来を心から心配しているからこその反対ですが、理解を得るまでには大変な労力と時間が必要です。
また、友人関係にも変化が生じることがあります。周りが恋愛や遊びを楽しんでいる中で、家庭を持つあなたとは話が合わなくなったり、疎遠になったりすることも。
世間からの「できちゃった結婚では?」といった偏見の目に、心を痛める場面もあるかもしれません。
学業やキャリアの選択肢が狭まる可能性
結婚生活や、それに伴うアルバイト・家事との両立は、学業に大きな影響を与えます。
勉強時間が確保できずに成績が下がったり、最悪の場合、進学や卒業を諦めざるを得ない状況も考えられます。
また、将来のキャリアプランにも制約が生まれる可能性があります。
就職活動で「若くして結婚している」という点が不利に働くケースもゼロではありませんし、転勤のある仕事や、時間的に不規則な職業を選ぶことが難しくなることもあります。
精神的な未熟さによるすれ違い
10代は、心も価値観もまだまだ成長途中の段階です。
今は「運命の人」だと感じていても、数年後、社会に出て様々な経験を積むうちに、考え方や人生の目標が大きく変わってしまうことは珍しくありません。
精神的に未熟なうちは、感情のコントロールが難しかったり、相手を思いやる余裕がなかったりして、些細なことから大きな喧嘩に発展しがちです。
理想と現実のギャップに悩み、「もっと他に良い人がいたかもしれない」と考えてしまうリスクも、若いからこそ高いと言えるでしょう。
世間的な信用を得にくい場合がある
社会的な信用度が低いと見なされ、生活の様々な場面で不便を感じることがあります。
例えば、アパートやマンションを借りる際の入居審査では、安定した収入や連帯保証人が重視されるため、10代の夫婦は審査に通りにくいことがあります。
同様に、クレジットカードの作成や、自動車ローン、住宅ローンといった各種ローンの契約も非常に難しくなります。
こうした社会的な信用の壁は、生活の自由度を大きく制限する要因となり得ます。
【最初の壁】親を説得するための完全ステップ
10代での結婚を決意したとき、多くの人が最初に直面するのが「親の説得」という大きな壁です。
感情的に反対されたり、心配されたりして、どうすれば理解してもらえるのか悩んでしまうかもしれません。
しかし、親が反対するのは、あなたの将来を心から心配している愛情の裏返しでもあります。
大切なのは、感情的に反発するのではなく、冷静に、そして誠実にふたりの覚悟と計画を伝えることです。
この章では、親の信頼を勝ち取り、祝福されて結婚するための具体的なステップを解説します。
なぜ親は10代の結婚に反対するのか?その心理を理解する
説得を始める前に、まずは「なぜ親は反対するのか」その心理を深く理解することが不可欠です。
親の心配の根源を知ることで、的確な説得材料を準備でき、話し合いをスムーズに進めることができます。
子どもの将来に対する経済的な心配
親が最も心配する点の一つが、経済的な問題です。
「まだ学生なのに、どうやって生活していくの?」「安定した収入もないのに、ふたりで暮らしていけるはずがない」と考えてしまうのは、親として当然の心境です。
特に、あなたたちがまだ高校生や大学生の場合、学費や生活費を親に頼っている状況かもしれません。
その状況で結婚するということは、親から見れば「経済的に自立できていないのに、さらに大きな責任を背負おうとしている」と映り、将来の生活破綻を危惧してしまうのです。
精神的な自立への不安
次に、精神的な未熟さへの懸念があります。
「まだ人生経験も浅いのに、大きな決断をするのは早すぎるのではないか」「恋愛感情だけで突っ走っていないか」「困難にぶつかったとき、ふたりで乗り越えていけるのか」といった不安です。
親はあなたを誰よりも長く見てきたからこそ、あなたの長所も短所も知っています。
若さゆえの過ちや、価値観の変化によって気持ちが揺らぐ可能性を心配し、「もっと広い世界を見てからでも遅くない」と考えてしまうのです。
世間体を気にする気持ち
意外と根深いのが「世間体」です。親戚やご近所、職場の人たちに「娘(息子)が10代で結婚することになった」とどう説明すればいいのか、頭を悩ませる親は少なくありません。
「できちゃった結婚だと思われるのではないか」「何か問題があったのではと勘繰られるのではないか」といった、周囲の目を気にしてしまうのです。
これは子どもの幸せを願う気持ちとは別の、親自身のプライドや社会的な立場に関わる問題であり、説得が難しい側面もあります。
親への挨拶と結婚の意思を伝える準備
親の心理を理解したら、次はいよいよ結婚の意思を伝える準備です。
この準備をどれだけ丁寧に行うかで、話し合いの結果は大きく変わります。
これは「許可を得る」場ではなく、「ふたりの覚悟を伝え、認めてもらう」ための大切な儀式だと心得ましょう。
まず最も重要なのは、パートナーと徹底的に話し合い、意思を統一しておくことです。
「なぜ結婚したいのか」「将来どんな家庭を築きたいのか」「学業や仕事はどうするのか」など、お互いの考えを深く共有し、覚悟を固めてください。
ふたりの意見が食い違っていたり、曖昧だったりすると、親の不安を煽るだけになってしまいます。
次に、挨拶に伺うタイミングと場所を選びます。
事前に「大切な話があるので、ふたりでご挨拶に伺いたい」とアポイントを取りましょう。
親が忙しい時間帯や、疲れている時間帯は避けるのがマナーです。
自宅でリラックスして話を聞いてもらえる環境がベストです。
当日の服装は、清潔感が第一です。
学生であれば制服、社会人であればスーツやジャケットを着用するなど、TPOに合わせたフォーマルな服装を心がけましょう。
誠実な印象を与えることが大切です。
また、感謝の気持ちを伝えるために3,000円~5,000円程度の手土産を持参するのが一般的です。
相手の親御さんの好みを事前にリサーチし、日持ちのするお菓子などを用意すると良いでしょう。
信頼を得るための具体的な説得材料
「結婚したい」という熱意だけでは、親の不安を解消することはできません。
信頼を得るためには、感情論ではなく、客観的で具体的な「説得材料」を提示することが不可欠です。
ふたりの将来設計やライフプラン
漠然とした夢物語ではなく、具体的な将来設計(ライフプラン)を作成し、書面で見せることが極めて有効です。
以下の項目を盛り込み、ふたりが真剣に将来を考えていることを示しましょう。
- 学業の計画:いつまでに高校・大学を卒業するのか。学費はどのように工面するのか。
- キャリアプラン:卒業後、どのような仕事に就きたいのか。そのために今どんな準備をしているのか。
- 住まいの計画:どこに住む予定か。家賃の目安はどれくらいか。
- 子どもの計画:将来的に子どもは欲しいか。いつ頃を考えているか。そのための準備はどうするか。
- 両親との関わり方:結婚後、それぞれの両親とどのように関わっていきたいか。
これらの計画を時系列でまとめることで、ふたりのビジョンが明確になり、親も具体的なイメージを持ちやすくなります。
具体的な収支計画と貯金額の提示
経済的な心配を払拭するための、最も強力な説得材料です。
現在の収入(アルバイト代など)と、結婚後の生活にかかる費用を具体的にシミュレーションした「収支計画表」を作成しましょう。
- 収入の部:ふたりのアルバイト代、奨学金、仕送りなど、月々の収入を全て書き出します。
- 支出の部:家賃、光熱費、水道代、通信費、食費、学費、保険料、お小遣いなど、想定される支出を細かく計算します。
この収支計画で、無理なく生活できることを数字で証明することが重要です。
さらに、現在ふたりで協力して貯めた貯金額を正直に提示しましょう。
たとえ金額が少なくても、「結婚に向けて計画的にお金を貯めてきた」という事実そのものが、ふたりの本気度を示す証拠となります。
お互いの両親との良好な関係構築
あなたの親を説得するためには、まずパートナーが自分の親から結婚の理解を得ていることが大前提です。
そして、「相手のご両親にも挨拶を済ませ、結婚を応援していただいています」と伝えられることは、非常に大きな安心材料となります。
また、あなたの親だけでなく、パートナーの親とも積極的にコミュニケーションを取り、良好な関係を築こうとする姿勢を見せましょう。
お互いの家族を大切に思う気持ちが伝われば、「このパートナーなら、自分の子どもを任せても大丈夫かもしれない」と親に感じてもらいやすくなります。
10代の結婚には、民法で定められている通り親の同意が必要です。
これは、未成年者を保護するための法律上のルールでもあります。
だからこそ、ここに挙げたような具体的な計画と誠実な姿勢をもって、親の不安に一つひとつ丁寧に向き合い、信頼を勝ち取ることが何よりも重要なのです。
【現実問題】10代の結婚生活に必要なお金の話
「好き」という気持ちだけで結婚生活を続けるのは、残念ながら難しいのが現実です。
特に、まだ社会人経験が浅い、あるいは学生である10代のカップルにとって、お金の問題は避けて通れない大きな壁となります。
ここでは、結婚に必要な初期費用から毎月の生活費、そして利用できる公的な支援制度まで、お金に関するリアルな話を具体的に解説します。
ふたりでしっかりと計画を立て、経済的な基盤を築くための一歩を踏み出しましょう。
結婚に必要なお金はいくら?初期費用を計算しよう
結婚を決めてから、ふたりでの新生活をスタートさせるまでには、まとまった「初期費用」が必要になります。
具体的にどのようなことにお金がかかるのか、項目別に見ていきましょう。
結婚式や指輪にかかる費用
結婚と聞いて多くの人がイメージする結婚指輪や結婚式。
これらにかかる費用は、選択次第で大きく変動します。
結婚指輪の費用
結婚指輪の相場は、ペアで20万円〜30万円程度が一般的です。
しかし、これはあくまで平均的な価格帯。
ブランドや素材(プラチナ、ゴールド、チタンなど)、デザインによって価格は大きく変わります。
最近では、ペアで10万円以下のリーズナブルな指輪も多くありますし、手作りできる工房などを利用して費用を抑えるカップルも増えています。
結婚式・披露宴の費用
一般的な結婚式・披露宴には、平均で300万円前後の費用がかかると言われています。
ご祝儀で一部をまかなえるとはいえ、10代のカップルがすぐに用意するのは非常に難しい金額です。
そのため、無理に大規模な式を挙げる必要はありません。
両家の親族だけを招いた食事会(10名で30万円〜50万円程度)、ウェディングドレスを着て写真だけを撮るフォトウェディング(5万円〜20万円程度)、婚姻届を提出するだけの「ナシ婚」など、費用を抑える選択肢はたくさんあります。
ふたりの経済状況に合わせて、身の丈に合ったお祝いの形を見つけることが大切です。
新生活の準備費用(引っ越し・家具・家電)
ふたりで暮らすための新居の準備にも、まとまったお金がかかります。
主に「引っ越し費用」と「新居の契約費用」、そして「家具・家電の購入費用」の3つに分けられます。
引っ越し費用:5万円~15万円
荷物の量や移動距離、引っ越し業者の繁忙期(3月〜4月)か閑散期かによって料金は変動します。
複数の業者から見積もりを取って比較検討しましょう。
新居の契約費用(敷金・礼金など):家賃の4~6ヶ月分
アパートやマンションを借りる際には、家賃だけでなく初期費用が必要です。
一般的に「敷金」「礼金」「仲介手数料」「前家賃」「鍵交換費用」「火災保険料」などがかかり、合計で家賃の4~6ヶ月分が目安となります。
例えば家賃7万円の部屋なら、28万円~42万円ほど必要になる計算です。
家具・家電の購入費用:30万円~50万円
冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、テレビ、ベッド、テーブル、カーテンなど、生活に必要なものを一から揃えるとなると、かなりの出費になります。
最初は最低限のものだけを揃え、少しずつ買い足していくのが現実的です。
また、リサイクルショップやフリマアプリを活用したり、親戚や友人から譲ってもらったりすることで、費用を大幅に抑えることができます。
これらを合計すると、結婚式の費用を除いても、新生活を始めるだけで最低でも50万円~100万円程度は必要になると考えておきましょう。
月々の生活費はどれくらい?収入と支出のシミュレーション
結婚生活は、初期費用を払って終わりではありません。
毎月安定した生活を送るためには、収入と支出のバランスをしっかりと管理する必要があります。
高校生や大学生カップルの収入源
10代カップルの主な収入源は、アルバイト代や、学生であれば親からの仕送り、奨学金などが考えられます。
正社員として働いている場合は、その給与が生活の基盤となります。
アルバイト収入の例
時給1,100円のアルバイトを、ふたりがそれぞれ週に20時間(1日5時間×週4日)ずつ行った場合、ひとりの月収は約88,000円。
ふたり合わせると約176,000円の収入になります。ここから税金や社会保険料が引かれる場合もあります。
高卒で就職した場合の収入
高校を卒業してすぐに就職した場合、初任給の平均は手取りで15万円~17万円程度です。
ボーナスの有無や金額は会社によって大きく異なります。
自分たちの収入がいくらになるのかを具体的に計算し、その範囲内で生活できるかを冷静に判断することが不可欠です。
家賃や食費など生活費の内訳
総務省の家計調査などを参考に、二人暮らしの1ヶ月の生活費のモデルケースを見てみましょう。
地域やライフスタイルによって金額は変動します。
- 家賃:70,000円(都心部を避けた場合の目安)
- 食費:50,000円(自炊中心の場合)
- 水道光熱費:20,000円
- 通信費(スマホ2台+ネット回線):15,000円
- 日用品・消耗品費:10,000円
- 交通費:10,000円
- 医療費:5,000円
- 保険料:10,000円
- 娯楽・交際費:20,000円
- その他雑費・貯金:20,000円
【合計:約230,000円】
このシミュレーションを見ると、アルバイト収入だけではかなり厳しい生活になることがわかります。
どちらか、あるいは両方が正社員として安定した収入を得ることが、現実的な選択肢となるでしょう。
家賃の安い地域に住む、自炊を徹底する、格安スマホに乗り換えるなど、支出を抑える工夫も必須です。
今からできる貯金方法と利用できる公的支援制度
経済的な不安を少しでも減らすために、今からできる貯金や、条件に合えば利用できる公的な支援制度について知っておきましょう。
まずは、ふたりで「1年後に〇〇万円貯める」といった具体的な目標を立て、共通の貯金用口座を作りましょう。
給料やアルバイト代が入ったら、まず決まった額をその口座に移す「先取り貯金」を習慣にすると、着実にお金を貯めることができます。
国の結婚新生活支援事業とは
これは、新婚世帯の経済的負担を軽減するために国が設けている制度です。
結婚を機に新生活を始める際の「新居の購入費や家賃」および「引っ越し費用」の一部を補助してくれます。
- 補助上限額:1世帯あたり最大30万円(夫婦共に29歳以下の世帯などは最大60万円)
- 主な対象要件:夫婦共に39歳以下であること、世帯所得が500万円未満であることなど。
この制度を利用するには、お住まいの市区町村がこの事業を実施している必要があります。
自分たちが対象になるか、また、お住まいの地域で実施されているかは、内閣府のホームページなどで確認できます。
地方自治体独自の支援制度
国の制度とは別に、市区町村が独自に新婚カップルを支援する制度を設けている場合があります。
「結婚祝い金」の給付や、住宅ローンの利子補給、家賃補助など、その内容はさまざまです。
自分たちが住んでいる、あるいはこれから住む予定の市区町村のホームページで「結婚 支援」「新婚 補助」といったキーワードで検索し、利用できる制度がないか必ずチェックしてみましょう。
こうした制度を賢く利用することも、安定した新生活を送るための大切なポイントです。
【完全解説】10代が結婚するための法律と手続きの流れ
「結婚したい」という強い気持ちがあっても、具体的に何をすればいいのか、法律や手続きのことは難しくてよくわからない、と感じるかもしれません。
特に10代での結婚は、特別な手続きが必要なのではと不安に思う方もいるでしょう。
この章では、結婚するために必要な法律の知識と、婚姻届の提出から結婚成立までの具体的な流れを、誰にでもわかるようにステップバイステップで詳しく解説します。
一つひとつの手続きを確実にクリアして、ふたりの新しい門出をスムーズに迎えましょう。
何歳から結婚できる?結婚可能年齢と親の同意の必要性
まず、法律で定められている「結婚できる年齢(婚姻適齢)」について正しく理解しておくことが重要です。
日本の法律(民法)では、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、結婚できる年齢も男女ともに18歳に統一されました。
つまり、18歳になっていれば、誰でも自分の意思で結婚することができます。
この法改正の重要なポイントは、18歳以上であれば、結婚にあたって親(親権者)の同意が法律上は不要になったことです。
以前は、20歳未満の未成年者が結婚する際には親の同意書が必要でしたが、現在は18歳、19歳の方も成人とみなされるため、同意書なしで婚姻届を提出できます。
ただし、法律上は同意が不要でも、これまで育ててくれたご両親に結婚を認めてもらい、祝福してもらうことは、これからの長い結婚生活において非常に大切なことです。
経済的な面や精神的な面で、ご両親のサポートが必要になる場面も出てくるかもしれません。
手続き上の話とは別に、ご両親への丁寧な説明と挨拶は必ず行い、円満な関係を築く努力をしましょう。
婚姻届の提出から結婚成立までの5ステップ
法律的な条件をクリアしたら、次はいよいよ具体的な手続きです。
婚姻届を提出し、法律上の夫婦として認められるまでの流れを5つのステップに分けて解説します。
ステップ1 婚姻届と必要書類の準備
まず、結婚の意思を公的に示すための「婚姻届」と、それに付随する書類を準備します。
婚姻届の入手
婚姻届の用紙は、全国の市区町村役場の戸籍担当窓口でもらえます。また、役所のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。最近では、デザイン性のあるおしゃれな婚姻届も販売されており、それらを使用することもできます。
必要書類
婚姻届とあわせて、次の書類が必要になります。
- 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)
本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合に必要です。ふたりとも本籍地以外の役所に提出する場合は、それぞれ1通ずつ用意します。戸籍謄本は、自分の本籍地がある市区町村役場で取得できます。郵送での取り寄せも可能ですので、遠方の場合は早めに手続きしましょう。 - 本人確認書類
窓口で手続きをする人の本人確認のために必要です。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの公的な身分証明書を持参してください。
ステップ2 親からの同意書の入手
【注意】このステップは、2022年4月1日の民法改正により不要になりました。
前述の通り、結婚可能年齢が18歳に引き上げられたことに伴い、18歳以上の方が結婚する場合、法律上の「親の同意書」は必要ありません。
婚姻届の「その他」欄にある同意の署名も不要です。
繰り返しになりますが、これはあくまで法律上の手続きの話です。10代で結婚するという大きな決断を、ご両親が心配するのは当然のことです。
同意書という形式は不要でも、ふたりの将来設計や覚悟をしっかりと伝え、心から応援してもらえるように、誠意をもって話し合うことが何よりも大切です。
ステップ3 証人を探す
婚姻届には、ふたりの結婚を証明してくれる「証人」2名の署名が必要です。
誰に頼む?
証人は、18歳以上の方であれば、親、兄弟姉妹、恩師、友人など、誰でもなることができます。
国籍も問いません。
一般的には、お互いの父親にお願いするケースが多いですが、お世話になった方や親しい友人に頼むのも素敵な記念になるでしょう。
お願いする際のマナー
証人をお願いする際は、事前に結婚の報告をした上で、証人になってほしい旨を丁寧にお願いしましょう。
証人には、氏名、生年月日、住所、そして本籍地を記入してもらう必要があります。
特に本籍地はすぐにわからない場合もあるため、事前に伝えておくとスムーズです。
署名は、証人本人に自筆で記入してもらう必要があります。
ステップ4 役所への婚姻届の提出
すべての書類が揃ったら、いよいよ役所に提出します。
提出先
婚姻届は、下記のいずれかの市区町村役場に提出できます。
- 夫になる人の本籍地または所在地
- 妻になる人の本籍地または所在地
「所在地」には、一時的な滞在地も含まれるため、旅行先の役所などで提出することも可能です。
提出日時と注意点
役所の開庁時間内に提出すれば、その場で職員が内容を確認し、不備がなければ「受理」されます。
もし書類に不備があった場合、その場で訂正できることもありますので、ふたりの旧姓の印鑑(認印で可)を持参すると安心です。
多くの役所では、土日祝日や夜間でも「時間外受付(夜間休日受付)」で婚姻届を預かってもらえます。
この場合、その場では「預かり」扱いとなり、翌開庁日に職員が内容を確認して、不備がなければ提出日に遡って受理されたことになります。
ただし、不備があると受理されず、後日連絡が来て修正のために役所へ出向く必要があるので、事前に開庁時間内に役所で内容をチェックしてもらう「事前審査」を受けておくと万全です。
ステップ5 戸籍の変更と各種名義変更
婚姻届が受理されると、法律上の夫婦となり、ふたりの新しい戸籍が作られます(または、どちらか一方の戸籍に配偶者が入る形になります)。
新しい戸籍が出来上がるまでには、1〜2週間程度かかるのが一般的です。
結婚後は、さまざまな名義変更手続きが必要になります。
特に名字が変わる側は手続きが多く大変ですが、計画的に進めましょう。
主な名義変更・手続きリスト
- 住民票の異動:住所が変わる場合は、転出届・転入届(または転居届)を提出します。婚姻届と同時に手続きできることが多いです。
- マイナンバーカード:氏名や住所の変更届が必要です。
- 運転免許証:新しい住民票を持参し、警察署や運転免許センターで記載事項の変更手続きをします。身分証明書として利用頻度が高いため、早めに変更するのがおすすめです。
- パスポート:氏名や本籍地が変わった場合、変更または新規発給の手続きが必要です。
- 銀行口座・クレジットカード:名義変更をしないと、給与の振込や引き落としに支障が出ることがあります。
- 携帯電話・スマートフォン
- 各種保険(健康保険、生命保険、医療保険など)
- 印鑑登録(名字が変わる場合)
これらの手続きは、何から手をつけるべきか混乱しがちです。
まずは「住民票」と「マイナンバーカード」の変更を行い、それらを証明書として「運転免許証」や「銀行口座」の変更を進める、というように順番を決めるとスムーズに進められます。
結婚後の生活はどうなる?学業や仕事との両立
10代での結婚は、ゴールではなく新しい生活のスタートです。
特に、多くの人が学生であったり、社会人として歩み始めたばかりの時期。
ここでは、結婚後の学業や仕事との両立について、具体的な課題と乗り越えるためのヒントを解説します。
高校・大学に通いながらの結婚生活
学生のうちに結婚する場合、これまでの生活とは大きく異なる現実に直面します。
しかし、計画的に準備を進めることで、学業と結婚生活を両立させることは十分に可能です。
学校生活への影響と手続き
まず知っておきたいのは、現在の日本の多くの高校や大学では、結婚を理由に退学を強制されることはないということです。
ただし、学校によっては校則で定められている場合もあるため、まずは学生便覧を確認したり、担任の先生や学生課の担当者に相談したりすることが大切です。
結婚の事実を学校に報告する義務があるか、どのタイミングで誰に伝えるべきかを確認しておきましょう。
また、姓が変わる場合の手続きも必要です。
学生証や各種登録情報を変更することになりますが、学校によっては旧姓の通称使用が認められるケースもあります。
友人関係などへの影響を考え、パートナーと相談して決めると良いでしょう。
奨学金や扶養の変更点
結婚によって世帯が一つになることで、奨学金の受給資格に影響が出ることがあります。
特に、親の収入を基準に審査されていた給付型奨学金や授業料減免制度は、配偶者の収入も合算して審査されることになります。
現在奨学金を利用している、あるいはこれから利用を考えている場合は、必ず日本学生支援機構(JASSO)や大学の奨学金担当窓口に確認しましょう。
同時に、これまで親の扶養に入っていた場合は、扶養から外れる手続きが必要になることもあります。
税金や社会保険に関わる重要なことなので、親ともしっかり話し合い、必要な手続きを進めてください。
学業と家事を両立させるためのタイムマネジメント
学生結婚で最も大きな課題となるのが、時間の使い方です。
授業への出席、レポートや試験勉強に加え、日々の炊事、洗濯、掃除といった家事がのしかかってきます。
どちらか一方に負担が偏らないよう、お互いの授業のコマ数やアルバイトの時間などを考慮し、家事の分担を明確に決めておくことが不可欠です。
スケジュール管理アプリなどを活用し、お互いの予定を共有するのも良い方法です。
仕事と家庭を両立させるためのポイント
社会人として働きながらの結婚生活は、経済的な安定が見込める一方で、仕事の責任と家庭生活の両立という新たな課題が生まれます。
ふたりで協力し、乗り越えていくための体制づくりが重要です。
家事・育児の分担ルールを明確にする
共働きが基本となる若い世代の結婚生活では、家事の分担が円満な関係を築く鍵となります。
「気づいた方がやる」という曖昧なルールは、結局どちらかの負担が大きくなりがちです。
お互いの勤務時間や体力も考慮し、「料理はAさん、ゴミ出しと風呂掃除はBさん」のように、具体的な分担を最初に決めておきましょう。
また、「名もなき家事」と呼ばれるような細々としたタスク(トイレットペーパーの補充など)もリストアップし、お互いが認識することが大切です。
お互いのキャリアプランを共有し応援し合う
10代は、キャリアの土台を築く非常に重要な時期です。結婚したからといって、どちらかのキャリアを諦める必要はありません。
お互いが将来どのような仕事に就きたいのか、どんな働き方をしたいのかをオープンに話し合い、尊重し合う姿勢が求められます。
「資格取得のために勉強したい」「将来的には転職も考えている」など、それぞれの目標を共有し、応援し合える関係を築きましょう。
コミュニケーションの時間を意識的に作る
仕事で疲れて帰ってくると、つい会話が少なくなりがちです。
しかし、忙しいからこそ、意識的にコミュニケーションの時間を確保することが重要です。
一緒に夕食を食べる、寝る前に10分だけその日あったことを話すなど、短い時間でも構いません。
感謝の気持ちやねぎらいの言葉を忘れずに伝え合うことが、すれ違いを防ぎ、強い絆を育みます。
妊娠や出産を考えたときの準備
若くして結婚した場合、早い段階で妊娠や出産を考えるカップルも少なくありません。
体力があるうちの子育てはメリットも大きいですが、経済的・精神的な準備が不可欠です。
計画的に進めるために、知っておくべきことを確認しましょう。
家族計画と経済的なシミュレーション
まずは「子どもはいつ頃欲しいか」「何人くらい欲しいか」といった家族計画について、ふたりでしっかりと話し合うことが第一歩です。
その上で、妊娠・出産・子育てにどれくらいのお金がかかるのかをシミュレーションしてみましょう。
出産費用そのものは、健康保険から支給される「出産育児一時金」で大部分をまかなえますが、妊婦健診の費用やベビー用品の購入など、何かと出費はかさみます。
子どもが生まれてからの生活費がどれくらい増えるのかも計算し、計画的に貯蓄を始めることが大切です。
利用できる公的な支援制度を調べる
日本には、子育て世帯を支えるための様々な公的制度があります。
これらを活用しない手はありません。
- 出産手当金:勤務先の健康保険に加入している女性が、出産のために仕事を休んだ場合に支給されます。
- 育児休業給付金:雇用保険に加入している人が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。男性も取得可能です。
- 児童手当:中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。所得制限があるため、ご自身の世帯が対象になるか確認が必要です。
これらの制度は、申請しなければ受け取ることができません。
お住まいの市区町村の役所のホームページや、厚生労働省のウェブサイトなどで情報を集め、利用できる制度は漏れなく活用しましょう。
産休・育休中の学業やキャリアプラン
子どもが生まれると、一時的に学業や仕事を中断する必要が出てきます。
学生の場合は、大学の休学制度を利用するのが一般的です。
復学後のプランまで見据え、指導教員や学生課に早めに相談しましょう。
社会人の場合は、法律で定められた「産前産後休業」や「育児休業」を取得できます。
休業中の収入を補うのが、先述の出産手当金や育児休業給付金です。
いつから休業に入るか、復帰の時期はどうするかなど、早めに勤務先と相談し、スムーズな引き継ぎができるよう準備を進めることが、円満な職場復帰につながります。
まとめ
10代で結婚することは、決して夢物語ではありません。
しかし、経済的な基盤の構築や親の説得など、乗り越えるべき現実的な課題も多く存在します。
この記事で解説したメリット・デメリットを二人で共有し、具体的なライフプランや資金計画を立てることが、周囲の信頼を得る第一歩です。
法的な手続きを正しく理解し、強い意志と覚悟を持って準備を進めれば、若くして幸せな家庭を築くことは十分に可能です。
二人の未来のために、一歩ずつ着実に進んでいきましょう。